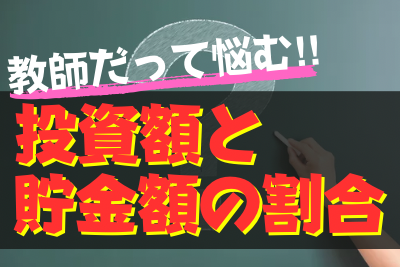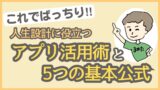こんにちは、教員まめたです。
前回は、教員の理想的な毎月の貯蓄額ついて解説しました。
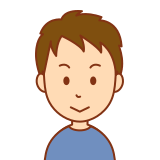
貯蓄率に注目するんだったね!
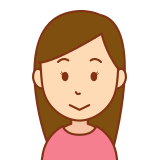
家計の見直しで余剰資金ができたよ!

でも、投資額と貯金額をどう決めたらいいの?
そんなふうにお悩みの先生は、
いらっしゃいませんか?
実際、私も同じでした…。
今回は、
貯蓄に回せるお金ができた教員向けに
「投資額と貯金額の割合の決め方」
について記事にしました。

この記事を読むことで、悩まず最適な資産形成ができるようになります!
・投資と貯金をバランスよくしたい
・子育てと貯蓄を両立させたい
・マイホームや結婚などに向けて貯金したい
まめたの自己紹介!!
・現役教師で、授業と子どもたちとの生活が好き。
・しかし、お金の知識不足で貯金できない生活や不安な日々を経験。
・それから教師の資産形成と金融教育に興味を持つように。
・猛勉強の末、FP2級、簿記3級、宅建の一発合格を果たす!
・今では、わが家の資産は右肩上がり中!!
☑︎お金を4つに分けよう
☑︎投資や貯金の目的と目標額を決めよう
☑︎投資割合は「100ー年齢」が王道
なんと、
- 預金率 54.2%
- 保険・年金商品で約30%
資産の80%が“現金“や“保険商品“なのです。
「現金が1番安心だね。」
「投資は危ない!」
という考えが浸透している現れですね。

何か問題あるの?
資産配分を間違えるリスク
資産配分を考えず、
十分な貯蓄なしに投資をすると…
- 生活に困る
- 資産をうまく増やせない
あなたには、どんな未来が見えますか?
- 働けなくなり収入0…
- 暴落で資産が半分に…
- 物価高で家計が苦しい…
- 親の介護に必要なお金がない…
- 病気や怪我で治療費がかかるのに払えない…
こうなっては生活に困りますよね。
さらに、興味深いデータがあります。

グラフから分かるように、
同じ20年間で金融資産が
アメリカは3.3倍伸びているのに
日本はわずか1.4倍。
日米間で2倍以上の金融格差が起きていますね。
その理由が分かりますか?
最初の図(家計の金融資産構成)をご覧ください。
実は、アメリカでは
資産運用が積極的に行われていた(投資率56.2%)
からです。
一方、超低金利が続く日本では
“預金“がメイン。
資産が増えないの当然ですよね。
こうした現実から
“資産形成の形を変えていく必要がある“
と言えないでしょうか。

投資を中心とした資産運用がポイントになりそうだね!

ここから詳しく説明していきます!
投資額と貯金額の決め方
大前提として、
投資額や貯金額は
年齢、家族構成、ライフステージ
によって異なります。
今回は基本的な考え方を
ご紹介していきますね。
お金を4つに分けよう
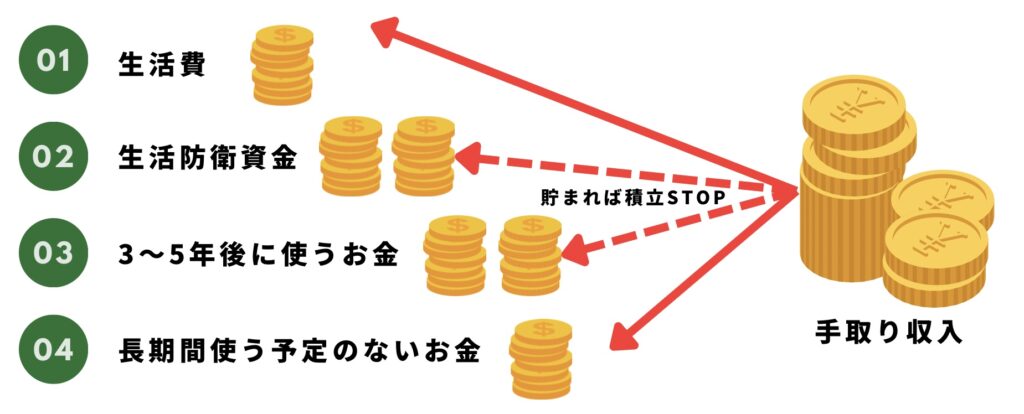
生活防衛資金を貯める

それぞれ詳しく教えて!
①生活費
1ヶ月暮らすのに必要なお金のことです。
- 食費
- 日用品
- 住居費
- 通信代
- 交通費
- 交際費
- 水道光熱費
- 美容・服飾費
- 趣味・娯楽費
- 毎月の返済額
これらのお金が
1ヶ月にどのくらいかかるのか把握しましょう。
まだ家計簿がない方への
おすすめはマネーフォワードMEです。
②生活防衛資金
緊急事態に備えるために
最優先して貯めるべきお金です。

最低生活費の3ヶ月〜1年分
最低生活費としたのは、
実家に帰れば家賃代や食費が浮くなどの状況を
考慮したためです。
最低生活費が20万円の人なら、
60〜240万円あれば十分でしょう。
教員の場合、
病気休暇、病気休職、傷病手当で
最長3年半の生活保障がある
ので、気持ち少なくてもいいのかもしれません。
③3〜5年後に使うお金
生活防衛資金が準備できたら
次に考えられるのが
教育費、住宅購入費、結婚・出産費などです。
預金や財形貯蓄で備えるのがオススメ
おおまかな目安は次のとおり↓

結婚費用は、
結婚式やハネムーンをするかしないかで
大きく変わってきます。
また、教員の場合
出産時に共済組合から給付金がもらえます。
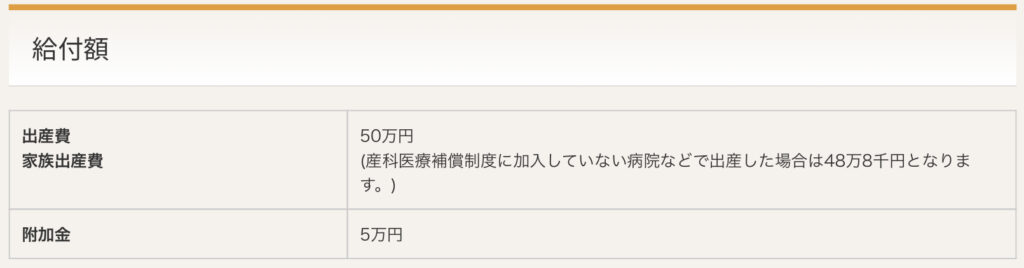
実質、負担金は0円に近いでしょう。
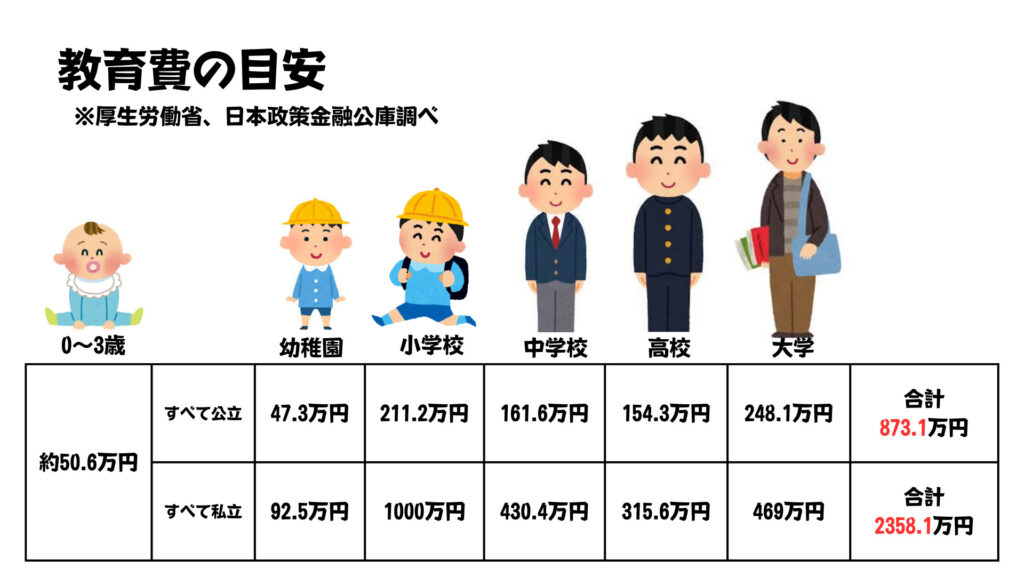

いずれにしても、
3〜5年後に必要なお金を
短期的な投資で増やそうとするのは
リスクの高い行為です。
それよりも、
必要なタイミングで“確実“に使えるように、
預金を中心とした準備が有力と考えられます。

短期投資でお金が減ったら困るしね。
④長期間使う予定のないお金
具体的には、
10年以上使う予定のないお金です。
自由度が高く、時間を味方にできるため
投資信託や新NISAなどの運用に回してもよいお金です。

ここまで4つに分けられましたか?
貯金や投資の目的、目標額を決めよう
- 何に(使い道)
- いつまで(期限)
- いくら(具体金額)
- 手段(投資or貯金等)
生活防衛資金が用意できた前提で
進めていきます。
例えば、次の事例を考えてみましょう。

このように逆算して考えると
必要な貯金額と投資額が分かりますね。
長期間使う予定のないお金は、
新NISAなどを活用しながら
資産として大きく育てていきたいところです。


流れが分かってきたよ!
年代別の投資比率を知ろう
100ー年齢

世界中で読まれている
“投資バイブル本”です。
「100ー年齢」という計算式は
本書で紹介されている考え方の1つです。
20代
投資:貯金=8:2
教員1〜2年目は生活防衛資金の準備で
大変かもしれませんが、
一度貯まれば長期運用の強みを生かしていけますよ!!

どういうこと?
投資における
最大の武器は何だと思います?
そう“時間”です。
教員をすぐ辞めない限り
毎月の収入でカバーできるので
運用リスクをとっていけるわけです。
20代から投資を始めれば
10年、20年、30年のように
“時間“という複利を利かせて
資産を増やせる可能性が高いのです。
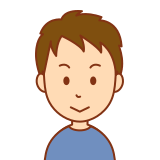
投資が初めてで不安なのですが…。
そうですよね、
私も最初はドキドキでした。
その場合は投資比率を5:5などから
始めてみてはいかがでしょう?
比率は自分に合わせて変えてOKです。
30〜40代
投資:貯金=7:3or6:4
この年代は
- 年収が増える時期
- ライフプランが大きく動きやすい時期
であります。
これらの点を踏まえて決めていきましょう。
ライフプランの設計や見直しを
考えている方はこちらもお読み下さい↓
50代以降
投資:貯金5:5〜3:7
この年代は、
- 老後に必要なお金を減らさない
- 株式から債券等への移行
が重要です。
教員を退職して年金や貯金で暮らすのが
一般的な流れでしたが、
人生100年と言われるように
長生きリスクも考えなければなりません。
価格変動の少ない“債券”等に移行することで、
リスクのバランスが取れると思います。

年代によって戦略が変わるんだね!
まとめ
最後までお読みいただき、
ありがとうございます!
“投資額と貯金額の割合の決め方“
はいかがでしたか?
「自分に適切な割合がわかった」
「リスクを取り過ぎていたことに気付けた」
「バランスよく資産を増やしていきたい」
などと、
みなさんの思考や行動が
変わりましたらうれしいです。
以上、教員まめたでした。
またお会いしましょう!

Twitterでも毎日発信しています。よろしければ、教員まめたのフォローをお待ちしております!