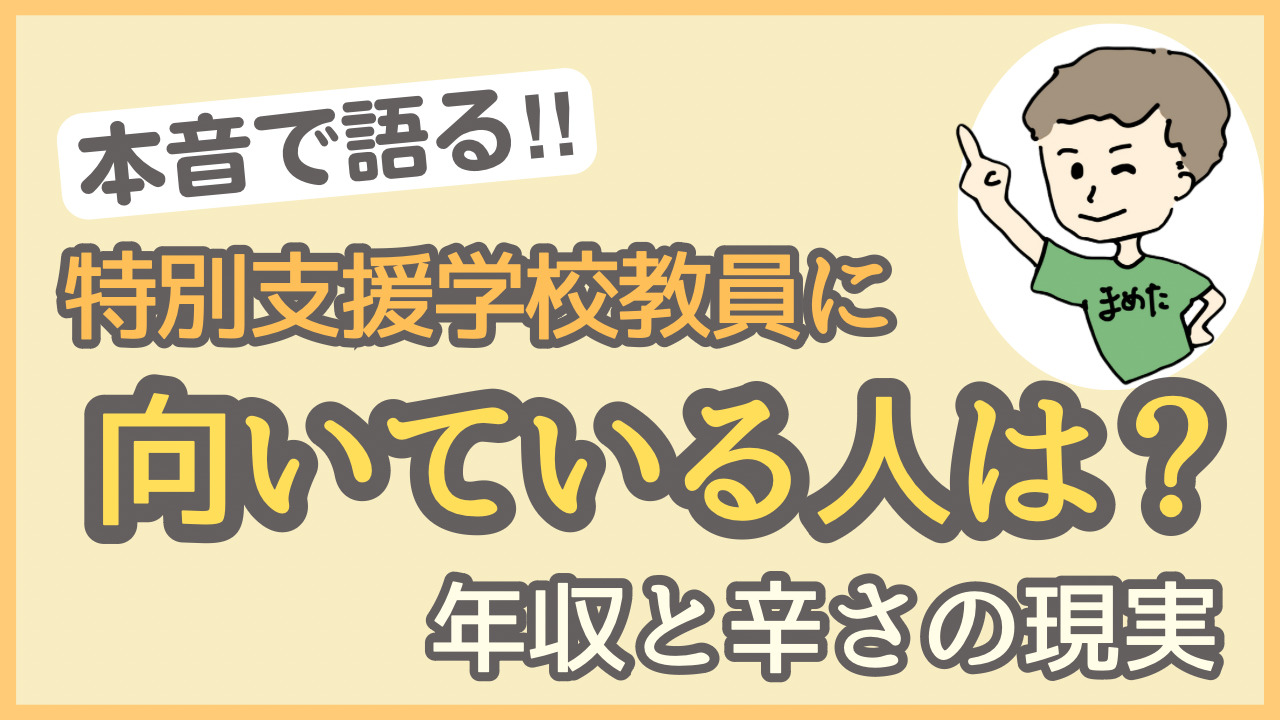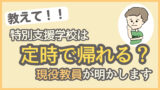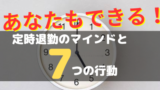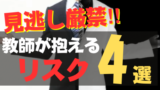「特別支援学校の教員に向いている人は?」
「小中よりも年収は高いけど、辛いの?」
「特別支援学校の教員として働いていて辛い。オススメの対応はある?」
たしかに特別支援学校には向いている人と向いていない人がいます。
年収が高い反面、特別支援学校ならではの辛さもあります。
結論から言いますと、特別支援学校のメリット・デメリットを理解した上で選択することが大切です。

こんにちは、教員のお金の話について発信中!特別支援学校現役教員(9年目)のまめたです。
- 授業と学校生活が好きな30代現役教師。
- 浪費家時代は、借金とわずかな貯金で不安な日々を経験。
- それから教師の資産形成と金融教育に興味を持つように。
- 勉強の末、FP2級、簿記3級、宅建を一発合格。
- 働く教師向けのお金の教室オープンし、発中。
- サイドFIREをめざすべく、資産家へ転身中!
- わが家の資産は5年で1000万円突破し、右肩上がり!
読者の方には、これから特別支援学校の教員として働こうとしている人や現役教員として働いている人がいる思います。
大学の講義や教育実習で特別支援に触れますが、実際に働いてみないとわからない面がたくさんあります。
現役教員でも、実際に働いてみての発見や気づきがあったのではないでしょうか?
壁にぶつかっている人も大勢いるでしょう。
今回は、特別支援学校教員に向いている人は?特別支援学校の年収や魅力、辛い現実とその対応について徹底解説。
☑︎特別支援学校教員には向き不向きがある
☑︎給料面の待遇とやりがいはあるが、辛さもそれなりにある
☑︎辛い現実への対応を知って今すぐ行動しよう
本記事をお読みいただければ、次の5つが理解できます。
- 特別支援学校に向いている人6選
- 特別支援学校の年収や給料事情
- 特別支援学校の魅力
- 特別支援学校教員の辛い現実
- 特別支援学校の辛い現実への対応
教員のお金が貯まる家計づくりについてLINEで発信中です!登録していただくと今なら『資産形成に役立つ7大特典』を無料でプレゼントしています。
ぜひ、LINE登録してプレゼントをお受け取りください
↓↓↓
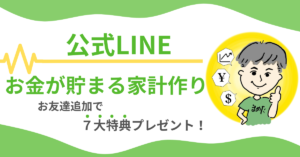
特別支援学校の教員に向いている人6選

特別支援学校の教員として向いている人の特徴6選↓
- 粘り強さがある人
- 気持ちをフラットに保てる人
- 日々のコミュニケーションをとれる人
- 傾聴力のある人
- 学ぶ意欲のある人
- 小さな気遣いができる人
粘り強さがある人
学習ペースがゆっくりだから
特別支援学校の児童生徒は、障がいの特性上、学習ペースがゆっくりです。
目標に対して、Aという指導支援をしたからといって必ず有効とは限りません。
そうなると、B、C、D…と様々な指導支援を試す必要があります。
学習も一度だけではなく、2回3回と繰り返し積み上げることで身に付けていきます。
こうした特性から、粘り強く児童生徒に指導できる人が向いています。

時間をかけて自分の力にしていく子が多いよね。
気持ちをフラットに保てる人
いろいろな場面が起こる
児童生徒と楽しく生活していても、
- 叱る場面
- 気長に待つ場面
- 暴言を受ける場面
- 支援がうまくできない場面
- 期待通りの姿が見られない場面など
に遭遇します。
そうしたときに感情のまま反応すると、お互いに泥沼にハマってしまいます。
心理的ストレスもかかりますし、適切な指導や支援も難しくなります。
だからこそ、どんな場面でも気持ちを安定させ、冷静に対応できる力が求められますね。

まずは大人が冷静じゃないとね。
日々のコミュニケーションをとれる人
児童生徒の変化を見逃さないため
特別支援学校では、個に応じた指導支援が必要です。
毎日かかわっていても、前日までとはちがう変化があったり、新たな困り感を示したりします。
自分の気持ちを上手く伝えられない児童生徒もいます。
そのような小さな変化や気持ちをキャッチし、適切な指導支援へつなげるために、日々のコミュニケーションが求められます。

教員同士のコミュニケーションは欠かせないよね。
傾聴力のある人
保護者と連携するため
通常学校でも当てはまりますが、特別支援学校の児童生徒の成長には特に“家庭の協力“が必要です。
- 食事
- 身支度
- あいさつ
- お金の遣い方
- 社会経験 など
将来の社会参加に向け、保護者との連携は欠かせません。
- 困り感
- 子どもの悩み
- 学校への要望
- 子どもに期待する姿
これらを共有するため、保護者の思いや悩みをつかむ傾聴力が求められます。

子どもの成長をみんなで支えるためだね!
学ぶ意欲のある人
専門性が必要だから
特別支援学校の児童生徒は様々な障がいを抱えています。
- 病弱
- 知的障がい
- 肢体不自由
- 難聴や弱視
- 自閉症スペクトラム症 など
だからといって、特別扱いすることは決してありません。
障がいも一つの個性であり、目の前にいる児童生徒だれもを一人の大人として接しています。
しかし、適切な指導支援を考えるために障がい理解は重要です。
そうした意味で、専門性のアップデートが求められます。

障がいによって支援の仕方も変わるからね。
小さな気遣いができる人
理由は以下の5つです↓
- 個別のニーズに対応するため
- 安心感と信頼感の構築のため
- 社会的スキルの向上のため
- 事故やケガの防止のため
- ストレスの軽減のため
特別支援学校には、様々な障がいや特別なニーズを必要とした児童生徒が通っているのでしたね。
- 危機回避の難しい児童生徒
- 言葉での表現が難しい児童生徒
- 小さな変化や訴えを見逃されやすい児童生徒など
細やかなサポートは、一人ひとりの成長だけでなく、生活上の安心安全へとつながります。

安心安全な学校が一番だからね!
特別支援学校の年収や給料事情

特別支援学校教員の年収と給料のポイント↓
小中学校よりも高い
特別支援学校の給料は、一人ひとりの障がいに対応する専門性を考慮され、高めに設定されています。
くわしい内容はこちらの記事で解説しています↓
特別支援学校の魅力
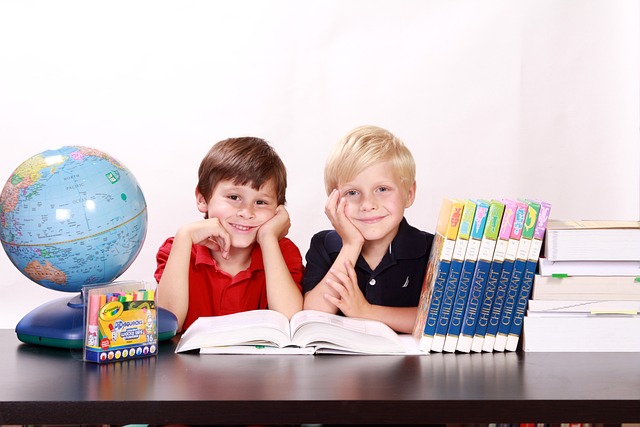
現役教員として感じる特別支援学校の魅力↓
- 成長を実感できる喜び
- 保護者からの感謝の言葉
- 授業づくりの面白さ
- 定時退勤のしやすさ
- 給与面での待遇
- 免許の取得しやすさ
成長を実感できる喜び
小さな成長が大きな喜びへ
特別支援学校の児童生徒はゆっくりと学んでいきます。
自分でできるようになるまで、時間もかかりますし、たくさんのチャレンジが必要です。
だからこそ、「小さなできた」が本人にも教員にも「大きな喜び」になりますね。
そのような成長を近くで感じられるのは、特別支援学校ならではでしょう。

子どもたちの自信にもつながるしね!
保護者からの感謝の言葉
関係の深い保護者からの感謝
特別支援学校の教員にとって、保護者とのコミュニケーションは欠かせません。
児童生徒の「できたこと」「がんばったこと」を共有できる関係だからこそ、感謝の言葉をいただくときがあります。
そんなとき、がんばって働いていてよかったと心から感じますね。

保護者はよきパートナーだからね!
授業づくりの面白さ
教科書のない授業
特別支援学校には、準ずる教育といって通常学校と同じように授業を行う学校もあります。
知的障がい学校では、準ずる教育だけでなく、児童生徒の特性に応じて授業を考えてよいと学習指導要領で示されています。
たとえば、カレーの調理学習を計画します。
- お金の勉強(算数)
- 野菜の名前(国語)
- カレーの歴史(社会)
- 調味料や具材選び(理科)
- 友達との話し合い(国語)
- お店まで買いに行く(社会)
このように、楽しい授業の中にも、各教科の要素を合わせることができます。
児童生徒は実際的な活動の中で、生活に必要な知識や技能を学んでいきます。
そうした意味で、教科書に縛られない柔軟な授業をできる面白さが特別支援学校にはあります。

生活単元学習は特別支援学校の醍醐味だよ!
定時退勤のしやすさ
働き方次第で定時退勤もできる
以下の記事のとおり、特別支援学校には定時退勤しやすい環境が整っています↓
働き方を日々磨くことで、定時退勤も決して難しいことではありません。
私もほぼ毎日定時退勤しています。
定時退勤に必要なマインドはこちら↓
給与面での待遇
小中学校よりも給与が高い
先ほども触れましたが、特別支援学校は、専門性を加味され給与も多めに設定されています。
大変な面もありますが、資産形成ではメリットもありますね。

小中で働く友人にも驚かれたよ!
免許の取得しやすさ
通信大学で1〜2年で取得できる
特別支援学校の免許には1種と2種があります。
通信大学なら、現役で教員をしながらでも免許を取得できます。
実習や演習はスクーリング会場もしくは大学や実習先に行く必要はあります。
しかし、それ以外は映像学習が中心です。
通信大学のメリット↓
- 学費の安さ
- 自分の生活に合わせて学べる
通信大学の難しさ(デメリット)↓
- モチベーション維持
- スケジュール管理

2種をとって特別支援学校に異動する人もいるよね!
特別支援学校の教員の辛い現実

実際に特別支援学校で働いて感じる辛い現実↓
- 職場の人間関係ストレス
- 児童生徒とのかかわりの難しさ
- 安全面
- 体力面
- 授業と教材研究の難しさ
- 保護者との関係
- 仕事内容に見合わない給料
- キャリアアップへの魅力のなさ
職場の人間関係ストレス
複数人体制が基本
特別支援学校はTT(team teaching)といって、2〜3人の教員がチームを組んで学級と学年を回していきます。
もちろん、児童生徒に適切な指導支援をするためです。
しかし教員も人間ですので相性があります。
- 働き方
- 価値観
- 家庭環境
- 得意不得意
こうしたことを擦り合わせながら働く必要があります。
相性が合えば問題ありませんが、逆の場合は大変です。
自分の思うような学級運営ができないだけでなく、1年間一緒に働くストレスがかなりかかるからです。
私がこれまで出会ったり、話を聞いたりしたモンスター教員↓
- 新しいことを学ばない
- 言動1つ1つに文句を言ってくる
- 仕事ができないのにプライドが高い
- 気が強くて自分の考えを曲げられない
- 歳をとっているから偉いと思っている
さらに、お局教員と組むときは注意が必要です。
私も妻と職場が同じだったとき、お局教員に目をつけられて、大変な目に遭いました。
児童生徒とのかかわりの難しさ
障がいによる個々のニーズの多様さ
特別支援学校には、多様なニーズをもった児童生徒がいます。
- 行動が読めない難しさ
- 成長や変化の見えにくさ
- 生死にかかわる瞬間がある
- 理解や技能の習得がとてもゆっくり
- その子に合った支援が見つからない難しさ
- 暴言や暴力など不適切な行動での意思表示
- 言葉や身振り、手話、視線、ジェスチャーでの意思表示など
こうした子ども達の姿も受け止めながら、かかわる姿勢が大切です。
私もコミュニケーションがうまくとれず、児童とぶつかるときもあります。
そんな場面でも、粘り強く冷静に対応しなければならない大変さはありますね。

児童生徒のことで日々悩むよね。
安全面
支援中のケガや事故
特別支援学校には、危険回避が難しかったり、行動が予想しにくかったりする児童生徒もいます。
- 誤食してしまう
- 道路に飛び出してしまう
- 体幹が弱く転倒しやすい
- 常にそばにいる必要がある
- 道具の安全な使い方がわからない
- 体温調整や水分補給が自分では難しい
こうした配慮事項に注意しながらの指導支援は、正直大変ですね。
さらに支援中に教員自身がケガをするケースも多いです↓
- 捻挫
- 打撲
- 切り傷
- ひっかき傷
- 歯が折れた
故意ではないとしても、お互いにケガをしないような支援を心がけています。

お互い安全に生活したいよね。
体力面
体を張る場面が多い
児童生徒の中には、様々な理由で暴れてしまう子もいます。
安全を確保するため、その子の体を一時的に押さえたり、別スペースに移動させたりする場面があります。
そうしたときに、教員が体を張って対応することもあるので、体力的も大変です。
体格がよく力のある児童生徒だと、複数人で対応することもあります。

中高生だと体も大きいしね。
授業や教材研究の難しさ
一人ひとりの特性に応じた計画
同じ学級にいるとはいえ、得意なことも苦手なこともみんなちがいます。
たとえば、音声優位な児童生徒もいれば、視覚優位な児童生徒もいます。
1つの授業をするにも多様な準備が必要となりますね。
- 個別の評価が難しい
- 授業の構成がわからない
- 自分が受けてきた授業とギャップがある
- 障がいに対する専門的な知識や経験が不足している
こうした悩みを抱える教員も多くいます。
だからこそ、児童生徒の学びや成長につながったときの達成感は大きいですね。

子どもの「わかった」「できた」姿はうれしいよね。
保護者との関係
連携の難しさ
協力的な保護者だけでなく、次のような保護者もいます↓
- 放任な保護者
- 暴言をぶつける保護者
- 学校への要望が多い保護者
もちろん、大切なわが子のための言動かもしれません。
しかし、学校と家庭の連携がなければ、子どもの成長につながりません。
忘れ物が多かったり、学級費の未納などで一番困るのは、子ども自身なのです。

保護者との信頼関係も不可欠だよね。
仕事に見合わない給料
精神的/身体的疲労の大きさ
教員の給料は経験年数と年齢に応じて、増えていきます。
初任者で20万円、9年目で27万円くらいです。
「今の給料で十分」と感じる人がいる一方、特別支援学校の大変さを考えたら「全然足りない」と感じる人もいますね。
このように給料面で不満を抱く教員がいることも事実です。

残業が多くなると、時給も下がる一方だしね。
キャリアアップへの魅力のなさ
管理職の魅力
教員として働くあなたに質問です。
将来、管理職になりたいですか?
私の答えは、NOです。
- 勤務時間の長い管理職
- 形式ばった面談や教員評価
- 働き方改革への期待感のなさ
- 悩みや困り事への対応の不十分さ
- 責任問題への対応(プールの漏水問題、部活動の事故など)
管理職に恵まれたこともありましたが、こうした理由から個人的にキャリアアップしたいと思いません。

なり手も少ないと聞くしね。
特別支援学校教員がぶつかる辛い現実への対応

これまでの経験を踏まえて、様々な辛さへの対応をご紹介します。
- 児童生徒のへの辛さ
- 職場の人間関係への辛さ
- 保護者への辛さ
- 給料面やキャリアアップへの辛さ
児童生徒への辛さ
- 周囲に相談する
- 実践を積んでいく
- ケース会を利用する
- 丁寧な観察を心がける
- 熱量と愛情を絶やさない
- 過去の指導案を参考にする
- 自分の得意な領域で頑張る
- セミナーや勉強会に参加する
完璧な教員はいません。
他人の力をたくさん借りながら、自分の経験値を高めていきましょう。

一人で抱え込まなくていいの!
職場の人間関係への辛さ
- 他人に期待しない
- 先輩や管理職への根回し
- 通常校への異動を希望する
- 積極的にコミュニケーションをとる
- 苦手な人や嫌な人とかかわる回数を減らす
私もモンスター教員と組んだときは、心の中で次のように思っていました。
- 気持ちを無にしよう
- この人は残念な人だ
- 自分の味方を増やそう
- あと◯時間/◯日で終わり
- この人に期待してがっかりするのはもったいない

職場ガチャとも言われるよね。
保護者への辛さ
- 主任や管理職に相談する
- 保護者の言葉を真に受けない
- 保護者の要望を100%受けない
これらが考えられる対応です。
- できないことは断る
- 専門的な根拠を示す
- 子どもの頑張ったことを伝える
こうした行動でも、あなたの大切な時間と体を守っていきましょう。

保護者対応に苦しむ同僚を何人も見てきたよ。
給料やキャリアアップへの辛さ
- 副業する
- プライベートを重視する
教員を続けるなら、この2つしか方法はないように思います。
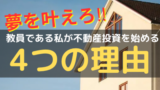
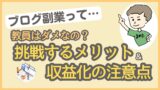
それでも辛さがなくならない教員へ
- 異動希望を出す
- 資格をとって選択肢を広げる
- 転職や退職、起業をする
そんなあなたには、自分の環境を変えることが一番の近道です。
通常学校に異動しても児童生徒の教育には貢献できますし、教員の仕事以外にも活躍できる場所があるはずです。
私も資格を取得したり、複数の転職サイトに登録したりしています。
オススメの資格↓
オススメの転職サイト↓

一度きりの人生だからね。
特別支援学校教員に向いている人は?年収と辛さの現実を本音で語る|まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます!
特別支援学校教員に向いている人は?年収と辛さの現実を本音で語るはいかがでしたか?
〈本日のまとめ〉
・特別支援学校教員には向き不向きがある
・給料面の待遇とやりがいはあるが、辛さもそれなりにある
・辛い現実への対応を知って今すぐ行動しよう
「特別支援学校に向いている人の特徴がわかった。」
「特別支援学校の辛さも知れてよかった。」
「自分にできる行動をしていこう。」
などと、みなさんの思考や行動が変わりましたらうれしいです。
ご意見や感想などは、管理人のまめたのX(@mameta_design)までぜひお寄せください。
以上、教員まめたでした。またお会いしましょう!