こんにちは。教員まめたです。
前回の記事では、教員が資格を取得するメリットを解説しました。
今回の記事では、さらに深掘りして【ぜったい騙されるな】教員が宅建資格を取得するメリット4選について解説します。
家買う先生のみなさん!一生に一度の大きな買い物で失敗しないように、不動産の知識を武装して準備しておきましょう!悪徳業者からみなさんの大切なお金を守りましょう!

近々マイホームを購入/売却される先生や、すでに家をお持ちの先生、不動産投資を始めようとしている先生、不動産の相続を予定している先生方の参考になれば嬉しいです!!
- マイホームの購入、所有、売却に役立つ
- 不動産投資に役立つ
- 実家等の相続時に役立つ
- 転職、就職活動、再就職での選択肢が増える→収入、年収UP
現役教員が宅建を取得するメリット
マイホームの購入・所有・売却に役立つ
1番のメリットです。教員でマイホームを購入される方はたくさんいると思います。普段の買い物と異なり、動く金額も大きく家計のバランスシートにも影響を与えます。知っておきたい事をキーワードにまとめました。
土地(中古)住宅選びにて
【都市計画法】
・用途地域(13つの目的に応じた地域が存在する)
・開発許可の有無(建築物の建築等のために行う土地の造成)
【建築基準法】
・道路規制(道路、接道義務)
・高さ制限(日当たりや火災を配慮した制限)
・建蔽率(敷地面積に対する建築面積の割合)
・容積率(敷地面積に対する建物の延べ面積の割合)
・防火地域・準防火地域(燃えにくい建物が必須になるかも)
【共有・区分所有法】
・マンションを購入した場合のあれこれ(専有部分や共用部分、敷地利用権、管理など)
【借地借家法】
・土地や家の借主が守られているのは何?
【土地・建物】
・台地、丘陵地、扇状地、低地、干拓地、埋立地など(住宅との相性)

キーワードは多いけど、土地や住宅を選ぶときのものさしを持てることはメリットとなりそうですね。
不動産の取得・所有・売却にかかる税金と控除
主な税金は以下の通りです。控除とは税金が安くなる措置のことを言います。
・相続税、贈与税(国税)
・登録免許税(国税。権利登記を受ける人に課される)
・印紙税(国税。課税文書を作成した場合に課される)
・不動産取得税(都道府県税。不動産を取得する際に課される)
・所得税(国税。譲渡による儲けに課される。住宅ローン減税も含む)
・固定資産税(市町村税。毎年1月1日に所有者として登録されている人に課される)

確かに税金の種類は多くて混乱しそうですが、何にお金を納めているのか知ることは大事です。費用の事前把握やランニングコストの計算にも役立ちそうです!
公示価格・鑑定評価額
土地価格や住宅価格の妥当性の判断は、素人には難しいものです。適正価格かもしれませんし、悪徳業者が利益をたっぷり含ませているかもしれません。そのような問題を考えるときに役立つのが、公示価格と鑑定評価額です。
公示価格とは、土地鑑定委員会がその地域における正常な価格を決定するものです。
鑑定評価額は主に3つあります。
・原価法による再調達原価(新しく同じように建てるとしたらいくら?造成するとしたらいくら?)
・取引事例比較法による比準価格(似た不動産の取引価格はいくら?)
・収益還元法による収益価格(賃料を想定した場合の価格はいくら?)

相場を知ることは不動産取引でも重要ですね。
業者とのトラブルを回避する
「業者は狼で、お客は羊。」と言われるほど両者の立場には差があります。
つまり、知識面でも金銭面でも不動産業者と対等に取引することが難しいのが現実です。
そうした一般消費者を保護するために宅建業法という法律があります。素人の私たちができることは業者の罠に気付くこと、トラブルを事前に回避することです。
以下、悪徳業者の罠やトラブル例です。
・損害補償トラブル
・手付金や預かり金トラブル
・不当表示、不当景品に該当する罠
・クーリングオフ制度の妨害トラブル
・業者への報酬額トラブル(上限がある)
・住宅の種類、品質、数量、権利が契約と異なるトラブル
・重要事項説明トラブル(必要な情報が説明されていない)
・担当した人が極悪な業者という罠(欠格事由に該当している)
・契約トラブル(考える時間なし、断定・威迫の禁止、取引態様)
こうした事例にも、宅建の知識は大変役立つと思います。

せっかくのマイホーム購入でトラブルはできるだけ避けたいですね。想定されるトラブルを知っておくだけで安心につながりますね。
その他
・不動産登記の仕組み
・自分の家が土地区画整理の対象になった場合の見通し
・自分の家が宅地造成等規制エリアの対象になった場合の見通し
不動産投資に役立つ
以下の場合、公務員の副業とはなりません。
4棟以下、9室以下、年間賃料収入500万円未満の規模
第2の収入源を得るため、私も物件を2022年夏から探しております。
自分が大家となり、自ら貸借することは取引に当たらないため、宅建士の免許は不要です。しかし、物件選びや費用計算、業者との交渉などで、とても宅建で得た知識が役立っています。
規模が大きくなり、教員を辞めた場合にもスムーズに事業移行できることもメリットかもしれません。

マイホーム購入と同じようにものさしを活用できるのですね。
実家等の相続時に役立つ
誰しも自分の家族から不動産を相続する機会や、子どもへの不動産の相続を考る機会があると思います。FP(ファイナンシャルプランナー)知識と重なる部分もありますが、宅建においても相続や贈与にかかる内容に触れることができます。(以下、例)
・遺産分割になったら?
・相続人が誰になるか?相続分は?
・農地を相続したら農業委員会に届け出が必要になる?

あらかじめ相続や贈与時の見通しをもっておくことで、いざというときでも焦らずに対応できそうですね!
転職/就職活動/再就職での選択肢が増える→収入、年収UP
さまざまな理由で教員を辞めた場合でも宅建資格を持っていることで、転職や就職活動、再就職に有利に働きます。
その理由は以下のとおりです。
・宅建業法により、不動産事務所は5人に1人の割合で宅建士を雇わなければなりません。そのため、宅建士は不動産業界で重宝されます。求人サイトを覗いてみても募集が多く見られます。
不動産業界の月収は比較的高く、宅建資格があることで資格手当がプラスされ、手取り額が増える会社も多いと聞きます。

宅建資格は取得しやすい国家資格として人気です。教員からの転職を支える資格としても心強いですね!
まとめ
現役教員にとってかけ離れたものと思われがちな不動産関連。
ところが、解説させていただいたように、教員にも関係する内容がたくさんありましたね。マイホーム購入〜売却、不動産投資、相続、転職などに備えて不動産の知識を武装しておくことは、自分や家族の安心・安全を保証する意味でとても大切だと思います。
私もまだまだ勉強している途中ですが、少しでも今回の記事が現役教員の皆さんにとって役立てば嬉しいです。
以上、教員まめたでした!!

それでは、またお会いしましょう!!


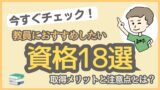
コメント